めもめも ...〆(。_。)
認知心理学・認知神経科学とかいろいろなはなし。 あるいは科学と空想科学の狭間で微睡む。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
作業の息抜きにふっとネットでニュースをちらちら見ていたら、「マスコミが人名を動詞化して流行語を作ろうとしている」みたいな記事が目に留まった。
「(人名)る」とか「(人名)する」とかそういうやつ。
もちろん現実にそんな単語使うひとなんていないんだけど、流行ってることにさせたいひとたちがいるらしい。
あーそんな話何年か前にもあったなー、と思って、その作られた単語一覧を見ていたら
モネートる
という単語があってえっ何マスコミさん今更スタージョン推しですかマジですかこれはSF黄金期の再来ですか今からスタージョンブームが来るのですか!と狼狽していたらめがさめた。
……ですよねー。
…うん、夢オチなんだすまない。
むしろそんな夢を見た自分にびっくりだよ!
「(人名)る」とか「(人名)する」とかそういうやつ。
もちろん現実にそんな単語使うひとなんていないんだけど、流行ってることにさせたいひとたちがいるらしい。
あーそんな話何年か前にもあったなー、と思って、その作られた単語一覧を見ていたら
モネートる
という単語があってえっ何マスコミさん今更スタージョン推しですかマジですかこれはSF黄金期の再来ですか今からスタージョンブームが来るのですか!と狼狽していたらめがさめた。
……ですよねー。
…うん、夢オチなんだすまない。
むしろそんな夢を見た自分にびっくりだよ!
カバーレターについていろいろ調べてたら前のめもは本当にひどい出来だなあと思ったので改めて書く。
まずぱっと目に付くだけのカバーレターサンプルを手に入れる。
http://www.jinrui.ib.k.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/wiki/wiki.cgi/letters?page=%A5%AB%A5%D0%A1%BC%A5%EC%A5%BF%A1%BC
http://mclcorp.s90.xrea.com/
http://blog.goo.ne.jp/paper-submit/e/efb7564df28a5662706c174e98dcc140
http://blog.goo.ne.jp/paper-submit/e/c64286ca07af24d70f249f670a404d22
http://ronbun.jp/cover/index.html
http://httrksk.blogspot.jp/2010/10/blog-post_12.html
http://pnp.forte-science.co.jp/module.cfm?mid=3&aid=77098C88FCD4A9
その他Tips的なもの
http://www.enago.jp/blog/%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
http://www.k-mec.jp/Hiketsu.html
http://dmed.co.jp/support/response_to_reviewers/
宛名はちゃんとEditorの代表者(なんか雑誌によって表現が違う)にしとく。
名前につけるtitle (Dr.なのかProfessorなのか)はどうするか微妙に迷うけど、名前ぐぐったらたいがいのひとは役職も判明するので保険として調べておく。
まあたいがいEditorになれるようなひとはProfessorなのでたいがいはProfessor宛に書く。
しかしEditorすら選べたりして誰宛にしていいのか本気でわからなくなる場合もある。
そのときはもうあきらめてDear Editorで書く。
APAマニュアルのカバーレターサンプルは
「I am enclosing a submission~」
で始まってるけど、これは封筒に原稿を入れて郵送してた時代の表現なので、これに代わる表現は何がいいのか悩んでいた。
サンプルいくつか見る限りでは、結局
「Please find our manuscript~」
的な表現が鉄板っぽい。
オンライン投稿がメインの今(オンライン投稿なのにカバーレターが要求されるのがそもそもめんどくさいよね!)、findもへったくれもないのではないかと思うのだが、まあ他にいい表現がないのでとりあえず出だしはこれを採用する。
あとの中身は、「絶対に」投稿雑誌のInstructionsに従うこと。
結構雑誌によって要求されてること違うみたいやし。
とりあえずわからんかったらAPAのを丸写しにする。
まあAPAならみんな知ってるだろうしいいか、というぶん投げ感。
と、いうことで心理用カバーレターのテンプレ的なものを改めて作り直してみる。
いやこれも不完全ですけどね。
「完全にかっこいいカバーレター」にたどりつくには、不完全なカバーレターを踏み台にしていくしかないのだ…
と言い訳しておく。
まあ自分用めもですから。あくまで自分用。
ーーーーーーー
Dear Professor (エディターの名前),
(あるいはDear Editor,)
Please find attached our manuscript entitled "(タイトル)" which we would like to be considered for publication in (雑誌名) as (記事の区分).
In the current study 論文の説明とかアピール
Some of the data from this paper were previously presented at 発表した学会の名前や日時、場所
There is no ethical problem or conflict of interest with regard to this manuscript.
(APAマニュアルにのってるように、
We followed APA ethical standards in the conduct of the study and all the participants in this study provided informed consent prior to joining the experiment. The procedure of the experiment adhered to Japanese legal requirements.
ぐらいていねいに書いたほうがいいかもしれん。そこはおこのみで)
Financial support for this study was provided byどこそこ(かけんひつかえるひとはちゃんとかけんひ番号もかかなあかんぽい)
(APAマニュアルに書いてあることをこぴぺするなら、
I will be serving as the corresponding author for this manuscript. All the authors have read the manuscript and have approved its submission. I have assumed responsibility for keeping my co-author informed of our progress throughout the editorial review process, the content of the reviews, and any revisions made. I understand that, if accepted for publication, a certification of authorship form will be required that my co-author will sign.
でもこれいらん可能性もわりとある)
Thank you for considering our manuscript.
Yours sincerely,
自分の名前
ーーーーーーー
だいたいこんなもんか。
まあ、さらっと流した「論文の説明とかアピール」が一番しんどいものな。
まあだいたいでいいや。だいたいで。
*****追記*****
前回は説明をつけてたけど、今回タイトルである「完全にかっこいい」の部分を説明してないので、ひょっとしてこれわたしが自信満々に書いてるように見えるんじゃないの?ということに気づいて今更あせってしまったり。
…あの、これ、だいぶ不十分ですよ。
「完全にかっこいい」というのは、「理想を追い求めたい、でも理想のものなんて存在しないのはわかっているという諦観はある、手元にあるものが理想とほど遠いこともわかっている、でも理想を追い求めちゃう」というような意味ですので。
「なんじゃその用法は」と思ったひとは、「完全にかっこいいカメラバッグ」で検索してみればこの用法に納得がいくかと思います。
いつか手に入れてみたいよなあ、完全にかっこいいカメラかばんと完全にかっこいいカバーレター。
************
まずぱっと目に付くだけのカバーレターサンプルを手に入れる。
http://www.jinrui.ib.k.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/wiki/wiki.cgi/letters?page=%A5%AB%A5%D0%A1%BC%A5%EC%A5%BF%A1%BC
http://mclcorp.s90.xrea.com/
http://blog.goo.ne.jp/paper-submit/e/efb7564df28a5662706c174e98dcc140
http://blog.goo.ne.jp/paper-submit/e/c64286ca07af24d70f249f670a404d22
http://ronbun.jp/cover/index.html
http://httrksk.blogspot.jp/2010/10/blog-post_12.html
http://pnp.forte-science.co.jp/module.cfm?mid=3&aid=77098C88FCD4A9
その他Tips的なもの
http://www.enago.jp/blog/%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
http://www.k-mec.jp/Hiketsu.html
http://dmed.co.jp/support/response_to_reviewers/
宛名はちゃんとEditorの代表者(なんか雑誌によって表現が違う)にしとく。
名前につけるtitle (Dr.なのかProfessorなのか)はどうするか微妙に迷うけど、名前ぐぐったらたいがいのひとは役職も判明するので保険として調べておく。
まあたいがいEditorになれるようなひとはProfessorなのでたいがいはProfessor宛に書く。
しかしEditorすら選べたりして誰宛にしていいのか本気でわからなくなる場合もある。
そのときはもうあきらめてDear Editorで書く。
APAマニュアルのカバーレターサンプルは
「I am enclosing a submission~」
で始まってるけど、これは封筒に原稿を入れて郵送してた時代の表現なので、これに代わる表現は何がいいのか悩んでいた。
サンプルいくつか見る限りでは、結局
「Please find our manuscript~」
的な表現が鉄板っぽい。
オンライン投稿がメインの今(オンライン投稿なのにカバーレターが要求されるのがそもそもめんどくさいよね!)、findもへったくれもないのではないかと思うのだが、まあ他にいい表現がないのでとりあえず出だしはこれを採用する。
あとの中身は、「絶対に」投稿雑誌のInstructionsに従うこと。
結構雑誌によって要求されてること違うみたいやし。
とりあえずわからんかったらAPAのを丸写しにする。
まあAPAならみんな知ってるだろうしいいか、というぶん投げ感。
と、いうことで心理用カバーレターのテンプレ的なものを改めて作り直してみる。
いやこれも不完全ですけどね。
「完全にかっこいいカバーレター」にたどりつくには、不完全なカバーレターを踏み台にしていくしかないのだ…
と言い訳しておく。
まあ自分用めもですから。あくまで自分用。
ーーーーーーー
Dear Professor (エディターの名前),
(あるいはDear Editor,)
Please find attached our manuscript entitled "(タイトル)" which we would like to be considered for publication in (雑誌名) as (記事の区分).
In the current study 論文の説明とかアピール
Some of the data from this paper were previously presented at 発表した学会の名前や日時、場所
There is no ethical problem or conflict of interest with regard to this manuscript.
(APAマニュアルにのってるように、
We followed APA ethical standards in the conduct of the study and all the participants in this study provided informed consent prior to joining the experiment. The procedure of the experiment adhered to Japanese legal requirements.
ぐらいていねいに書いたほうがいいかもしれん。そこはおこのみで)
Financial support for this study was provided byどこそこ(かけんひつかえるひとはちゃんとかけんひ番号もかかなあかんぽい)
(APAマニュアルに書いてあることをこぴぺするなら、
I will be serving as the corresponding author for this manuscript. All the authors have read the manuscript and have approved its submission. I have assumed responsibility for keeping my co-author informed of our progress throughout the editorial review process, the content of the reviews, and any revisions made. I understand that, if accepted for publication, a certification of authorship form will be required that my co-author will sign.
でもこれいらん可能性もわりとある)
Thank you for considering our manuscript.
Yours sincerely,
自分の名前
ーーーーーーー
だいたいこんなもんか。
まあ、さらっと流した「論文の説明とかアピール」が一番しんどいものな。
まあだいたいでいいや。だいたいで。
*****追記*****
前回は説明をつけてたけど、今回タイトルである「完全にかっこいい」の部分を説明してないので、ひょっとしてこれわたしが自信満々に書いてるように見えるんじゃないの?ということに気づいて今更あせってしまったり。
…あの、これ、だいぶ不十分ですよ。
「完全にかっこいい」というのは、「理想を追い求めたい、でも理想のものなんて存在しないのはわかっているという諦観はある、手元にあるものが理想とほど遠いこともわかっている、でも理想を追い求めちゃう」というような意味ですので。
「なんじゃその用法は」と思ったひとは、「完全にかっこいいカメラバッグ」で検索してみればこの用法に納得がいくかと思います。
いつか手に入れてみたいよなあ、完全にかっこいいカメラかばんと完全にかっこいいカバーレター。
************
ひさしぶりにパワポのテンプレつくったよー。
そろそろ紅葉シーズンなのでもみじテンプレ。
秋っぽい!!!
もう冬みたいなもんなのに。
タイトル画面はこんなんで、
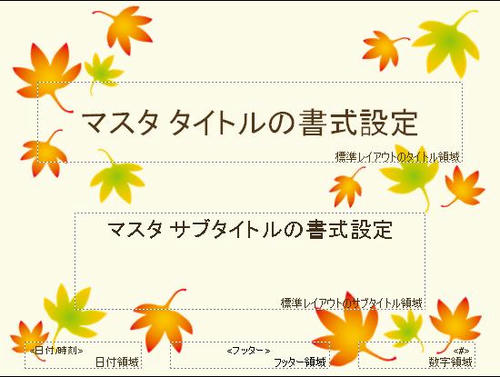
本文のところはこんなかんじです。

よかったらどぞー。
ダウンロード(pot)
そろそろ紅葉シーズンなのでもみじテンプレ。
秋っぽい!!!
もう冬みたいなもんなのに。
タイトル画面はこんなんで、
本文のところはこんなかんじです。
よかったらどぞー。
ダウンロード(pot)
いやもうタイトルそのまんまの話なんですが。
英文校正をお願いしたら、化学専門の担当者に当たっちゃったっぽい。
統計の基本的用語につっこみいれられたり、倫理規定話ざっくり削られたりしちゃったよ!
無駄に疲れた。
そういや化学とか物理とかは統計つかわないんだっけ?
工学部出身の友達がそんなようなこと言ってた気がする(違ったらごめん)。
あと生き物扱わないひとは当然倫理規定なにそれおいしいの?になるわな・・・
分野が違うと「常識」がとことん違うことにびっくりしたよ!当たり前だけどな!
てゆーか領域指定できなかったのだろうか・・・?
当たり前だけど、校正会社によってとくいな分野と苦手な分野とあるんですね。
いやそれ以前に、雑誌の出版社によっては、推薦業者とか公開してくれてるところあるんじゃん!!!
http://www.springer.jp/news/20111122000892.php
とか
http://journalauthors.tandf.co.uk/benefits/resources.asp
とかね。
・・・次の機会があったら、投稿したい雑誌の出版社推薦業者に依頼したいと思います。
そのほうがお互いにとっていいと思う。
「いやいやそんなことすら知らなかったのかよ」って言われそうですが。
英文校正をお願いしたら、化学専門の担当者に当たっちゃったっぽい。
統計の基本的用語につっこみいれられたり、倫理規定話ざっくり削られたりしちゃったよ!
無駄に疲れた。
そういや化学とか物理とかは統計つかわないんだっけ?
工学部出身の友達がそんなようなこと言ってた気がする(違ったらごめん)。
あと生き物扱わないひとは当然倫理規定なにそれおいしいの?になるわな・・・
分野が違うと「常識」がとことん違うことにびっくりしたよ!当たり前だけどな!
てゆーか領域指定できなかったのだろうか・・・?
当たり前だけど、校正会社によってとくいな分野と苦手な分野とあるんですね。
いやそれ以前に、雑誌の出版社によっては、推薦業者とか公開してくれてるところあるんじゃん!!!
http://www.springer.jp/news/20111122000892.php
とか
http://journalauthors.tandf.co.uk/benefits/resources.asp
とかね。
・・・次の機会があったら、投稿したい雑誌の出版社推薦業者に依頼したいと思います。
そのほうがお互いにとっていいと思う。
「いやいやそんなことすら知らなかったのかよ」って言われそうですが。
図(とおおざっぱな内容)しか覚えていない論文がどうしても読みたくなって、でもそんな体たらくでは文字検索に頼れないのでもう人力で文献フォルダひっくりかえして探してたら、「あ、これおもしろいっぽいじっくり読みたい」という論文が出てきたのでそれをめも。
過去のろんぶんめもともしかぶりがあってもきにしない。
あと今忙しいのでPubMedリンクとか貼らない。
Quantitative modeling of the neural representation of objects: How semantic feature norms can account for fMRI activation
Chang, Mitchell & Just NeuroImage 56 (2011) 716–727
あれこれ前読んだ気がする。
Feature Normsをdecodingにかけたってやつ
Cue dynamics underlying rapid detection of animals in natural scenes
Elder & Velisavljević JournalofVision (2009)9(7):7,1–20
Rapid scene categorizationが形・テクスチャ・輝度・色のうちどれを手がかりにしてるか
どうぶつはやっぱ形じゃね?色とか輝度とかはイラネ
(色なしでCategorizationできるってのは他でも言われてたと思う)
What can saliency models predict about eye movements? Spatial and sequential aspects of fixations during encoding and recognition
Foulsham & Underwood Journal of Vision (2008)8(2):6,1–17
Saliencyは再認に影響するか?
眼球運動とってる
Scrambled eyes? Disrupting scene structure impedes focal processing and increases bottom-up guidance
Foulsham, Alan & Kingstone 2011 Atten Percept Psychophys
シーン画像をスクランブルしたら視覚探索も記憶もパフォーマンス低下するというのを眼球運動とってじっくり
Ultra-Rapid Categorization of Fourier-Spectrum Equalized Natural Images: Macaques and Humans Perform Similarly.
Girard Koenig-Robert (2011) PLoS ONE 6(2):e16453. doi:10.1371/journal.pone.0016453
サルもRapid Categorizationする
Where Do Objects Become Scenes?
Kim & Biederman 2011 Cerbral Cortex
あのBiedermanが著者に入ってる!
オブジェクトとシーンはどう違うのか?という話。
確かに気になる・・・けど操作してるのはオブジェクト同士の距離かよ。
いやまあそれも大事だけど。うん。
ちゃんと読んでから考える。
Oculomotor capture during real-world scene viewing depends on cognitive load
Matsukura, Brockmole, Boot & Henderson Vision Research 51 (2011) 546–552
めんどくさいことすると眼球運動もめんどくさいという話(ひどい超訳)
Ignoring the Elephant in the Room: A Neural Circuit to Down regulate Salience
Mevorach, Hodsoll, Allen, Shalev, and Humphreys The Journal of Neuroscience, 28,2010 30(17):6072–6079
Saliencyの高いものを抑制するときの神経基盤。
タイトルで笑った。
自分の部屋で想像したらそりゃうざいわ。
Creating false memories for visual scenes
Miller and Gazzaniga 1997 Neuropsychologia
き○ーピー3分間虚偽記憶の作り方。
今日はあのGazzaniga先生にお越しいただきました。
というノリで読んでみたい論文。
内容的にはDRMパラダイムを画像でやろうぜ!ってことっぽい気がする。
TMS to the Lateral Occipital Cortex Disrupts Object Processing but Facilitates Scene Processing
Mullin & Steeves Journal of Cognitive Neuroscience 2011
オブジェクトとシーンは何が違うんだ研究の流れか。
タイトルがまんま中身を表してくれててわかりやすいですね。
こんなにぱっきり方向性がわかれるTMSならたしかにおもしろい。
ERP evidence for context congruity effects during simultaneous object–scene processing.
Mudrik, Lamy & Deouell Neuropsychologia (2009)
へんな場面ってやつのERP
The effect of non-visual working memory load on top-down modulation of visual processing
Rissman, Gazzaleya, D'Esposito Neuropsychogia 2009
ワーキングメモリモデル的にはモダリティの違う情報処理ってそんなに負荷にならんって話やったけどそうでもないかもよということか。
What line drawings reveal about the visual brain.
Sayim and Cavanagh (2011) Front.Hum.Neurosci. 5:118.
線画研究まとめ。
Neural structures and mechanisms involved in scene recognition: A review and interpretation
Sewards Neuropsychologia 2011
scene recognitionのreview
Orienting Attention Based on Long-Term Memory Experience
Summerfield, Lepsien, Gitelman, Mesulam and Nobre 2006 Neuron 49,905–916
シーンにおける注意とLTM
Natural Scene Categories Revealed in Distributed Patterns of Activity in the Human Brain
Walther, Caddigan, Li Fei-Fei, and Beck The Journal of Neuroscience,26,2009 • 29(34):10573–10581
Rapid scene categorizationをPPAとかでデコーディングする話
Color aids late but not early stages of rapid natural scene recognition.
Yao & Einhäuser(2008). Journal of Vision, 8(16):12,1–13
Rapid scene categorizationで色情報がやくにたつのはわりとおそいらしい
Bayesian Reconstruction of Natural Images from Human Brain Activity
Naselaris, Prenger, Kay, Oliver and Gallant Neuron 2009
初期視覚野+視覚経路の前のほう+画像のもつ意味情報でデコーディング
前情報あるのってどうなん?
Simple line drawings suffice for functional MRI decoding of natural scene categories
Walther, Chai, Caddigan, Beck and LiFei-Fei 2011 PNAS
線画のデコーディング
で、ここまで探しても目当ての論文が見つからないという悲劇。
どこいったんだ?
てゆかどこで見たんだ自分?
まさか、夢で見たとかじゃないよな。
まさかな。
過去のろんぶんめもともしかぶりがあってもきにしない。
あと今忙しいのでPubMedリンクとか貼らない。
Quantitative modeling of the neural representation of objects: How semantic feature norms can account for fMRI activation
Chang, Mitchell & Just NeuroImage 56 (2011) 716–727
あれこれ前読んだ気がする。
Feature Normsをdecodingにかけたってやつ
Cue dynamics underlying rapid detection of animals in natural scenes
Elder & Velisavljević JournalofVision (2009)9(7):7,1–20
Rapid scene categorizationが形・テクスチャ・輝度・色のうちどれを手がかりにしてるか
どうぶつはやっぱ形じゃね?色とか輝度とかはイラネ
(色なしでCategorizationできるってのは他でも言われてたと思う)
What can saliency models predict about eye movements? Spatial and sequential aspects of fixations during encoding and recognition
Foulsham & Underwood Journal of Vision (2008)8(2):6,1–17
Saliencyは再認に影響するか?
眼球運動とってる
Scrambled eyes? Disrupting scene structure impedes focal processing and increases bottom-up guidance
Foulsham, Alan & Kingstone 2011 Atten Percept Psychophys
シーン画像をスクランブルしたら視覚探索も記憶もパフォーマンス低下するというのを眼球運動とってじっくり
Ultra-Rapid Categorization of Fourier-Spectrum Equalized Natural Images: Macaques and Humans Perform Similarly.
Girard Koenig-Robert (2011) PLoS ONE 6(2):e16453. doi:10.1371/journal.pone.0016453
サルもRapid Categorizationする
Where Do Objects Become Scenes?
Kim & Biederman 2011 Cerbral Cortex
あのBiedermanが著者に入ってる!
オブジェクトとシーンはどう違うのか?という話。
確かに気になる・・・けど操作してるのはオブジェクト同士の距離かよ。
いやまあそれも大事だけど。うん。
ちゃんと読んでから考える。
Oculomotor capture during real-world scene viewing depends on cognitive load
Matsukura, Brockmole, Boot & Henderson Vision Research 51 (2011) 546–552
めんどくさいことすると眼球運動もめんどくさいという話(ひどい超訳)
Ignoring the Elephant in the Room: A Neural Circuit to Down regulate Salience
Mevorach, Hodsoll, Allen, Shalev, and Humphreys The Journal of Neuroscience, 28,2010 30(17):6072–6079
Saliencyの高いものを抑制するときの神経基盤。
タイトルで笑った。
自分の部屋で想像したらそりゃうざいわ。
Creating false memories for visual scenes
Miller and Gazzaniga 1997 Neuropsychologia
き○ーピー3分間虚偽記憶の作り方。
今日はあのGazzaniga先生にお越しいただきました。
というノリで読んでみたい論文。
内容的にはDRMパラダイムを画像でやろうぜ!ってことっぽい気がする。
TMS to the Lateral Occipital Cortex Disrupts Object Processing but Facilitates Scene Processing
Mullin & Steeves Journal of Cognitive Neuroscience 2011
オブジェクトとシーンは何が違うんだ研究の流れか。
タイトルがまんま中身を表してくれててわかりやすいですね。
こんなにぱっきり方向性がわかれるTMSならたしかにおもしろい。
ERP evidence for context congruity effects during simultaneous object–scene processing.
Mudrik, Lamy & Deouell Neuropsychologia (2009)
へんな場面ってやつのERP
The effect of non-visual working memory load on top-down modulation of visual processing
Rissman, Gazzaleya, D'Esposito Neuropsychogia 2009
ワーキングメモリモデル的にはモダリティの違う情報処理ってそんなに負荷にならんって話やったけどそうでもないかもよということか。
What line drawings reveal about the visual brain.
Sayim and Cavanagh (2011) Front.Hum.Neurosci. 5:118.
線画研究まとめ。
Neural structures and mechanisms involved in scene recognition: A review and interpretation
Sewards Neuropsychologia 2011
scene recognitionのreview
Orienting Attention Based on Long-Term Memory Experience
Summerfield, Lepsien, Gitelman, Mesulam and Nobre 2006 Neuron 49,905–916
シーンにおける注意とLTM
Natural Scene Categories Revealed in Distributed Patterns of Activity in the Human Brain
Walther, Caddigan, Li Fei-Fei, and Beck The Journal of Neuroscience,26,2009 • 29(34):10573–10581
Rapid scene categorizationをPPAとかでデコーディングする話
Color aids late but not early stages of rapid natural scene recognition.
Yao & Einhäuser(2008). Journal of Vision, 8(16):12,1–13
Rapid scene categorizationで色情報がやくにたつのはわりとおそいらしい
Bayesian Reconstruction of Natural Images from Human Brain Activity
Naselaris, Prenger, Kay, Oliver and Gallant Neuron 2009
初期視覚野+視覚経路の前のほう+画像のもつ意味情報でデコーディング
前情報あるのってどうなん?
Simple line drawings suffice for functional MRI decoding of natural scene categories
Walther, Chai, Caddigan, Beck and LiFei-Fei 2011 PNAS
線画のデコーディング
で、ここまで探しても目当ての論文が見つからないという悲劇。
どこいったんだ?
てゆかどこで見たんだ自分?
まさか、夢で見たとかじゃないよな。
まさかな。
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリ説明
もっさり:日々の雑感をもっさり。
がっつり:論文や研究関連をがっつり。
びっくり:科学ニュースでびっくり。
まったり:空想科学などでまったり。
ばっかり:デザイン系自己満足ばっかり。
ほっこり:お茶を嗜んでほっこり。
がっつり:論文や研究関連をがっつり。
びっくり:科学ニュースでびっくり。
まったり:空想科学などでまったり。
ばっかり:デザイン系自己満足ばっかり。
ほっこり:お茶を嗜んでほっこり。
最新コメント
※SPAMが多いのでhttpを含むコメントと英語のみのコメントを禁止しました※
最新記事
(05/08)
(04/24)
(04/10)
(02/03)
(11/01)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
az
性別:
非公開
自己紹介:
興味のあるトピックス
分野は視覚認知。視知覚にがて。
あと記憶全般。
カテゴリ (semanticsか?) とかも。
最近デコーディングが気になる。
でも基本なんでもこい。
好奇心は悪食。
好きな作家(敬称略)
川上弘美
小林秀雄
津原泰水
森茉莉
レイ・ブラッドベリ
イタロ・カルヴィーノ
グレッグ・イーガン
シオドア・スタージョン
分野は視覚認知。視知覚にがて。
あと記憶全般。
カテゴリ (semanticsか?) とかも。
最近デコーディングが気になる。
でも基本なんでもこい。
好奇心は悪食。
好きな作家(敬称略)
川上弘美
小林秀雄
津原泰水
森茉莉
レイ・ブラッドベリ
イタロ・カルヴィーノ
グレッグ・イーガン
シオドア・スタージョン
ブログ内検索
最古記事
(08/05)
(08/16)
(08/19)
(08/19)
(08/21)
カウンター
フリーエリア
PR


